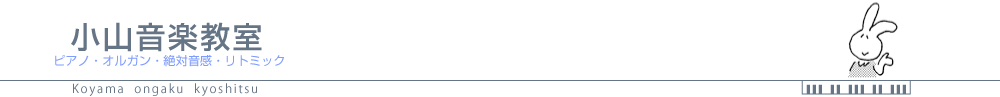「留守」
「ちょっと留守にするだけだ」
手術のため、京都に出発する前日に、父は母にこう言いました。
7月の初め、新潟はまだそんなに暑くない頃です。
これから夏に向かうという中、母は夏を終えて、秋も越えて、冬になった時の事を心配していました。
寒い季節に父に頼っていた事、自分ひとりでどうしたらいいのか、父に聞いていたのです。
「帰ってくるよ!」
ひとつひとつ説明するのが、もう面倒、という感じで父は答えました。
父が新潟に帰るより、母も京都に来たらいいのに。
そう思いながら、私は両親のそんなやりとりを黙って見ていました。
ちょっと留守にするだけのはずだった父が、2度と戻らなくなった新潟の家で、今も母はひとりで暮らしています。
母は時々、自分の作った俳句を送ってきます。
此処に居る 夫と生ききし この炉辺に
共に来し この炉を守り 生きつづく
慣れた場所 慣れた暮らしや 至福の炉
母にとっては、新潟に暮らすことが、父と共にいることなのかもしれません。
「ちょっと留守にするだけだ」
手術のため、京都に出発する前日に、父は母にこう言いました。
7月の初め、新潟はまだそんなに暑くない頃です。
これから夏に向かうという中、母は夏を終えて、秋も越えて、冬になった時の事を心配していました。
寒い季節に父に頼っていた事、自分ひとりでどうしたらいいのか、父に聞いていたのです。
「帰ってくるよ!」
ひとつひとつ説明するのが、もう面倒、という感じで父は答えました。
父が新潟に帰るより、母も京都に来たらいいのに。
そう思いながら、私は両親のそんなやりとりを黙って見ていました。
ちょっと留守にするだけのはずだった父が、2度と戻らなくなった新潟の家で、今も母はひとりで暮らしています。
母は時々、自分の作った俳句を送ってきます。
此処に居る 夫と生ききし この炉辺に
共に来し この炉を守り 生きつづく
慣れた場所 慣れた暮らしや 至福の炉
母にとっては、新潟に暮らすことが、父と共にいることなのかもしれません。
「腰を抜かす」
腰が抜けるって、こういう状態の事をいうんだなあ。
父の居るホスピスに母を連れていったその時、私はエントランスのソファに一度腰掛けた後、立ち上がることが出来なくなってしまいました。
父が亡くなる、3日前の事です。
人間、大変な時におかしな事が頭に浮かぶものらしく、その時わたしは「ああ、腰って本当に抜けるんだ」と、そんな事を考えていました。
父が治療のため京都に来てから約3ヶ月半、母は父と全く会っていませんでした。
耳が遠くて電話も聞こえないため、電話で話したこともありませんでした。
父の意識のあるうちに、母を京都に連れてこなければ…
母ともう一度会わないまま、父を逝かせるわけにはいかない…
その日、早朝に目が覚めた瞬間、母を連れてくるなら今日しかない、と思い、寝ている主人に今日新潟に行くと告げ、「迎えに行くから、京都に来る準備をしておくように」と母にFAXを入れ、ふたりの娘の学校を休ませ一日ホスピスの父のそばで過ごすよう言い渡し、空港へ向かうバスの中からホスピスに連絡を入れ、文字通り飛行機で飛んで新潟に行きました。
新潟の家では、母が既にコートを着込んで待っていました。
5分と家にいなかったと思います。全く座る事もありませんでした。
とんぼ返りもいいところです。
帰りは飛行機が満席で、新幹線を乗り継ぐことになったと母に伝えます。
「飛行機は怖いから、新幹線の方がいいわ」
80過ぎて、足も不自由な母と乗るんだからと、グリーン席に乗り込みました。
「せまいわね」
参ったな…でも、これはいつもの母のノリです。
いつもの調子なら、やれやれです。
やせ細った父の姿を見たら、どんなに驚くだろう。
まだホスピスに誤解の残る母に、少しでもホスピスでの生活の良い所を伝えなければ。
母と再会する時、父の意識は大丈夫だろうか…
耳がすっかり遠くなった母とは、帰りの新幹線の中では筆談で話しました。
少しでも、びっくりしないように。
少しでも、安心させてあげられるように。
少しでも、いい再会ができるように。
ホスピスで待つ娘達にメールを入れると
「おじいちゃん、おばあちゃんに会うためにお風呂に入れてもらって、今寝てるよ」
そう返信がありました。
母に筆談で伝えると「まあ」と 少し照れたように笑います。
ホスピスのスタッフの方の配慮が、娘のメールの行間から伝わります。
あと少し、あと少し。
新幹線を乗り継ぎ、混み合う京都駅を出て、再びタクシーを飛ばしてホスピスに向かう頃には、もうすっかり夜になっていました。
真っ暗な坂道をタクシーで上っていくと、ホスピスの明かりが見えてきました。
その明かりは、マッチ売りの少女のマッチの灯のように、現実のものではないように浮き上がって見えました。
ホスピスのエントランスでは、娘達が笑顔で待っていてくれました。
仕事を終えた夫が、ほぼ同時にホスピスに到着して迎えてくれました。
あと少し、
あと少しで病室なのに…
もう一度立ち上がって、病室まで母を連れて行くことが、私にはできませんでした。
娘達が母に付き添ってくれ、夫は私の隣に残ってくれました。
こんな事って、あるんだな。
腰が抜けたまま、しばらく思考も、時間も止まってしまい、その日のその後の事は今もあまり思い出せずにいます。
腰が抜けるって、こういう状態の事をいうんだなあ。
父の居るホスピスに母を連れていったその時、私はエントランスのソファに一度腰掛けた後、立ち上がることが出来なくなってしまいました。
父が亡くなる、3日前の事です。
人間、大変な時におかしな事が頭に浮かぶものらしく、その時わたしは「ああ、腰って本当に抜けるんだ」と、そんな事を考えていました。
父が治療のため京都に来てから約3ヶ月半、母は父と全く会っていませんでした。
耳が遠くて電話も聞こえないため、電話で話したこともありませんでした。
父の意識のあるうちに、母を京都に連れてこなければ…
母ともう一度会わないまま、父を逝かせるわけにはいかない…
その日、早朝に目が覚めた瞬間、母を連れてくるなら今日しかない、と思い、寝ている主人に今日新潟に行くと告げ、「迎えに行くから、京都に来る準備をしておくように」と母にFAXを入れ、ふたりの娘の学校を休ませ一日ホスピスの父のそばで過ごすよう言い渡し、空港へ向かうバスの中からホスピスに連絡を入れ、文字通り飛行機で飛んで新潟に行きました。
新潟の家では、母が既にコートを着込んで待っていました。
5分と家にいなかったと思います。全く座る事もありませんでした。
とんぼ返りもいいところです。
帰りは飛行機が満席で、新幹線を乗り継ぐことになったと母に伝えます。
「飛行機は怖いから、新幹線の方がいいわ」
80過ぎて、足も不自由な母と乗るんだからと、グリーン席に乗り込みました。
「せまいわね」
参ったな…でも、これはいつもの母のノリです。
いつもの調子なら、やれやれです。
やせ細った父の姿を見たら、どんなに驚くだろう。
まだホスピスに誤解の残る母に、少しでもホスピスでの生活の良い所を伝えなければ。
母と再会する時、父の意識は大丈夫だろうか…
耳がすっかり遠くなった母とは、帰りの新幹線の中では筆談で話しました。
少しでも、びっくりしないように。
少しでも、安心させてあげられるように。
少しでも、いい再会ができるように。
ホスピスで待つ娘達にメールを入れると
「おじいちゃん、おばあちゃんに会うためにお風呂に入れてもらって、今寝てるよ」
そう返信がありました。
母に筆談で伝えると「まあ」と 少し照れたように笑います。
ホスピスのスタッフの方の配慮が、娘のメールの行間から伝わります。
あと少し、あと少し。
新幹線を乗り継ぎ、混み合う京都駅を出て、再びタクシーを飛ばしてホスピスに向かう頃には、もうすっかり夜になっていました。
真っ暗な坂道をタクシーで上っていくと、ホスピスの明かりが見えてきました。
その明かりは、マッチ売りの少女のマッチの灯のように、現実のものではないように浮き上がって見えました。
ホスピスのエントランスでは、娘達が笑顔で待っていてくれました。
仕事を終えた夫が、ほぼ同時にホスピスに到着して迎えてくれました。
あと少し、
あと少しで病室なのに…
もう一度立ち上がって、病室まで母を連れて行くことが、私にはできませんでした。
娘達が母に付き添ってくれ、夫は私の隣に残ってくれました。
こんな事って、あるんだな。
腰が抜けたまま、しばらく思考も、時間も止まってしまい、その日のその後の事は今もあまり思い出せずにいます。
「手ぬぐい」
父の入院中、ある事がきっかけで“余韻の残る介護をしたい”と思うようになりました。
入院してしばらく経った頃、父の洗面用に手ぬぐいにあるような和風の柄のガーゼタオルを用意しました。藍色の地模様に、赤い金魚が泳いでいるような柄です。
そのタオルをベッドに寝ていて見えるところに掛けておいたので、私が帰ったあと、父はその柄をじっと眺めていたのだと思います。
翌日、父は私に教え子の話をしました。
ある日、もう30は過ぎたであろう ひとりの教え子から、結構立派な日本の紋様の本が届けられたそうです。
「先生、お元気ですか。僕は今、こんな勉強をしています」
という内容の手紙が添えられていたそうです。
「なぜか、突然、送ってきたんだなあ」
父はそう言いました。 父は絵心のある人だったので、教え子さんも そんな父の一面を子供ながらに感じて、覚えていてくださったのでしょうか。
「へええ、素敵な話ね」
本当に素敵な話だなあ、と思いました。
巣立った教え子からの元気な便りは、先生にとってこの上なく嬉しいもののはずです。
嬉しかったことを思い出す時間は、楽しいものだったことでしょう。
「昨日、おまえが持って来た手ぬぐいの柄を見ていて、そんな事を思い出した」
父はそう言ってくれました。
私が帰った後、ベッドの中でひとり過ごす長い時間に、余韻の残る介護がしたい。
そう思ったのはそのときからです。
ある日、看護師長さんが、多忙な中時間を作って父の病室を訪ねてくださいました。
「わたしの実家は、牛を育てているんですよ」
そんな話を、ゆっくり父に話してくださいました。本当にゆったりと…
次の日、父は私に言いました。
「あれから、ずっと牛の事を考えていた」
え〜、牛の何について考えていたんだろう。
「牛の腸は、どうなっているんだろうなあ」
さすがに、直腸の手術を終えたばかりの患者さんです。
牛は食べた物を反芻することを思い出して、私は父に聞きました。
「反芻するのは、無意識に反芻しているのかしら。それとも、もういちど噛もう、って思って反芻するのかしら」
「そりゃ、もう一度噛もう、って思うんだろう」
大真面目に父は答えました。
正しい答えが見つかるような、見つからないような…師長さんの話から、翌日になっても続く平和なゆったりとした時間…。
さすが、やり手の師長さん!すばらしい“余韻の残る看護”を、ありがとうございました。
父の入院中、ある事がきっかけで“余韻の残る介護をしたい”と思うようになりました。
入院してしばらく経った頃、父の洗面用に手ぬぐいにあるような和風の柄のガーゼタオルを用意しました。藍色の地模様に、赤い金魚が泳いでいるような柄です。
そのタオルをベッドに寝ていて見えるところに掛けておいたので、私が帰ったあと、父はその柄をじっと眺めていたのだと思います。
翌日、父は私に教え子の話をしました。
ある日、もう30は過ぎたであろう ひとりの教え子から、結構立派な日本の紋様の本が届けられたそうです。
「先生、お元気ですか。僕は今、こんな勉強をしています」
という内容の手紙が添えられていたそうです。
「なぜか、突然、送ってきたんだなあ」
父はそう言いました。 父は絵心のある人だったので、教え子さんも そんな父の一面を子供ながらに感じて、覚えていてくださったのでしょうか。
「へええ、素敵な話ね」
本当に素敵な話だなあ、と思いました。
巣立った教え子からの元気な便りは、先生にとってこの上なく嬉しいもののはずです。
嬉しかったことを思い出す時間は、楽しいものだったことでしょう。
「昨日、おまえが持って来た手ぬぐいの柄を見ていて、そんな事を思い出した」
父はそう言ってくれました。
私が帰った後、ベッドの中でひとり過ごす長い時間に、余韻の残る介護がしたい。
そう思ったのはそのときからです。
ある日、看護師長さんが、多忙な中時間を作って父の病室を訪ねてくださいました。
「わたしの実家は、牛を育てているんですよ」
そんな話を、ゆっくり父に話してくださいました。本当にゆったりと…
次の日、父は私に言いました。
「あれから、ずっと牛の事を考えていた」
え〜、牛の何について考えていたんだろう。
「牛の腸は、どうなっているんだろうなあ」
さすがに、直腸の手術を終えたばかりの患者さんです。
牛は食べた物を反芻することを思い出して、私は父に聞きました。
「反芻するのは、無意識に反芻しているのかしら。それとも、もういちど噛もう、って思って反芻するのかしら」
「そりゃ、もう一度噛もう、って思うんだろう」
大真面目に父は答えました。
正しい答えが見つかるような、見つからないような…師長さんの話から、翌日になっても続く平和なゆったりとした時間…。
さすが、やり手の師長さん!すばらしい“余韻の残る看護”を、ありがとうございました。