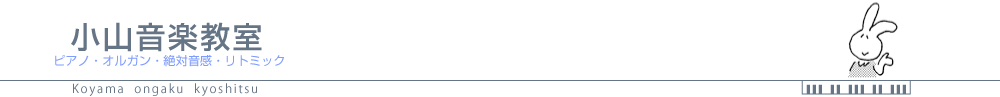「本」
子供の頃、父の書斎にもぐり込んで、こっそり父の本を読むのが好きでした。
何を読んだのか、今となってはあまり記憶にありませんが、「校長先生の朝のおはなし集」を見つけた時にはとっても愉快な気持ちになったことを覚えています。
だって父は“校長先生”でしたから。
父が亡くなった後、帰省した時にも父の書斎に入りました。
懐かしいなあと思いながら、ふと見ると「ホスピス・ケア」という本が目に入りました。
20年ほど前の日付で、購入時の記録が裏表紙にメモしてありました。
(父には、そういう習慣がありました)
手が震えるほどに驚きました。
ホスピスに入院する為には、入院する本人が自分が がん である事はもちろん、病状や、治療についても理解していないと入院できません。
そのため胸のつぶれそうな思いで、でもそれを悟られないように張りつめた気持ちで
「ホスピスが一番いいと思う」と、
父には私が説明をしたのです。
父はすんなり「おまえがそう言うんなら、それがいいんだろう」と静かに答えました。
「ホスピスに行くよ」
最初から、父はすべて知っていたんだ。
父の本棚から見つけた、20年前のホスピスの本を読みました。
さすがに今とはだいぶ状況が違うようで、素人ながらケアの方法、お薬の使い方など、現在の方がずっと研究が進んで、進歩しているのはよくわかりました。
でも、ホスピスが決して「死を待つ所」ではなく「生きる所」だということは、今と変わらず、読者にむけて強調して記されていました。
ホスピス転院が決まって、リハビリに励んでいた父。
明日に希望を持って、ホスピスに行ったらなにを趣味にしようか、と思いを巡らせていた父。
父が希望を持って過ごせていたのは、看護士さんはじめ、病院スタッフのみなさんの適切なアプローチとサポートがあったからに違いありません。
でもそれだけではなく、父自身が持っていた誤解のないホスピスについての知識がベースにあったことも大きかったのだと、その本は教えてくれました。
どうして父が20年も前にその本を手にしていたのか…
今となっては、知るすべがありません。
子供の頃、父の書斎にもぐり込んで、こっそり父の本を読むのが好きでした。
何を読んだのか、今となってはあまり記憶にありませんが、「校長先生の朝のおはなし集」を見つけた時にはとっても愉快な気持ちになったことを覚えています。
だって父は“校長先生”でしたから。
父が亡くなった後、帰省した時にも父の書斎に入りました。
懐かしいなあと思いながら、ふと見ると「ホスピス・ケア」という本が目に入りました。
20年ほど前の日付で、購入時の記録が裏表紙にメモしてありました。
(父には、そういう習慣がありました)
手が震えるほどに驚きました。
ホスピスに入院する為には、入院する本人が自分が がん である事はもちろん、病状や、治療についても理解していないと入院できません。
そのため胸のつぶれそうな思いで、でもそれを悟られないように張りつめた気持ちで
「ホスピスが一番いいと思う」と、
父には私が説明をしたのです。
父はすんなり「おまえがそう言うんなら、それがいいんだろう」と静かに答えました。
「ホスピスに行くよ」
最初から、父はすべて知っていたんだ。
父の本棚から見つけた、20年前のホスピスの本を読みました。
さすがに今とはだいぶ状況が違うようで、素人ながらケアの方法、お薬の使い方など、現在の方がずっと研究が進んで、進歩しているのはよくわかりました。
でも、ホスピスが決して「死を待つ所」ではなく「生きる所」だということは、今と変わらず、読者にむけて強調して記されていました。
ホスピス転院が決まって、リハビリに励んでいた父。
明日に希望を持って、ホスピスに行ったらなにを趣味にしようか、と思いを巡らせていた父。
父が希望を持って過ごせていたのは、看護士さんはじめ、病院スタッフのみなさんの適切なアプローチとサポートがあったからに違いありません。
でもそれだけではなく、父自身が持っていた誤解のないホスピスについての知識がベースにあったことも大きかったのだと、その本は教えてくれました。
どうして父が20年も前にその本を手にしていたのか…
今となっては、知るすべがありません。
「荷造り」
ホスピス転院予定の2日前だったでしょうか。
朝、病室に向かう途中、看護士さんから
「お父様、荷造りしていらっしゃって…」
と声をかけられました。
荷造り?と思って病室に入ると、きちんと片付けられたサイドテーブルを前に父はベッドの上に起き上がっていました。
引き出しの中味は分類されて袋の中へ、輪ゴムのかかっているものもあります。
食事に使うお箸やフォークも、しっかり、袋の中です。
「ホスピスに行くのはまだ先よ。片付けちゃったらご飯食べられないじゃない」
「…そうか?」
父の場合、直腸がんが見つかったときには既に、肝臓に数カ所の転移がありました。
ホスピス転院を前に、思いの外早く肝臓への転移による痛みがきていて、モルヒネを使い始めていました。
父も私も、いろんな意味で一番辛かった頃です。
いえ、父の辛さは、私の想像をはるかに超えたものだったと思います。
身体的にも、精神的にも。
いろいろたくさん混乱している中で、ホスピスへの転院のために少しでも自分で出来る事は自分でしようと思ったのでしょう。
どんなに小さい事でも、いつでも自分でしようとしていた父でしたから。
食事を前に、きれいに荷造りされた荷物をほどきました。
少し、もったいないような気持ちでした。
ホスピス転院予定の2日前だったでしょうか。
朝、病室に向かう途中、看護士さんから
「お父様、荷造りしていらっしゃって…」
と声をかけられました。
荷造り?と思って病室に入ると、きちんと片付けられたサイドテーブルを前に父はベッドの上に起き上がっていました。
引き出しの中味は分類されて袋の中へ、輪ゴムのかかっているものもあります。
食事に使うお箸やフォークも、しっかり、袋の中です。
「ホスピスに行くのはまだ先よ。片付けちゃったらご飯食べられないじゃない」
「…そうか?」
父の場合、直腸がんが見つかったときには既に、肝臓に数カ所の転移がありました。
ホスピス転院を前に、思いの外早く肝臓への転移による痛みがきていて、モルヒネを使い始めていました。
父も私も、いろんな意味で一番辛かった頃です。
いえ、父の辛さは、私の想像をはるかに超えたものだったと思います。
身体的にも、精神的にも。
いろいろたくさん混乱している中で、ホスピスへの転院のために少しでも自分で出来る事は自分でしようと思ったのでしょう。
どんなに小さい事でも、いつでも自分でしようとしていた父でしたから。
食事を前に、きれいに荷造りされた荷物をほどきました。
少し、もったいないような気持ちでした。
「平穏」
身近な誰かを失った時、心の平穏を取り戻すことは難しいことです。
「心の平穏を取り戻されることを、お祈り致しております」
そう言ってもらって、すぐに心が平穏になることなどないし、それで取り戻せるくらいのものだったら、もともとそんなに心は「平穏」からそう遠くないところにあるのかもしれない。
それでも「平穏」という言葉を聞くだけで、心が平穏に向かって方向転換できそ
うな気がしてくるのは、私だけでしょうか。
これは所謂“言霊”というものだろうかとも考えましたが、今はそれよりも、その
言葉を自分に届けてくれる“人”の存在が、力になっていたような気がしています。
たくさん、助けられてここまで来ました。
「心の平穏を取り戻されることを、お祈りしています」
今、心が平穏から遠く離れてしまっている人がいたら、今度はわたしからこの言葉を届けたいと思います。
身近な誰かを失った時、心の平穏を取り戻すことは難しいことです。
「心の平穏を取り戻されることを、お祈り致しております」
そう言ってもらって、すぐに心が平穏になることなどないし、それで取り戻せるくらいのものだったら、もともとそんなに心は「平穏」からそう遠くないところにあるのかもしれない。
それでも「平穏」という言葉を聞くだけで、心が平穏に向かって方向転換できそ
うな気がしてくるのは、私だけでしょうか。
これは所謂“言霊”というものだろうかとも考えましたが、今はそれよりも、その
言葉を自分に届けてくれる“人”の存在が、力になっていたような気がしています。
たくさん、助けられてここまで来ました。
「心の平穏を取り戻されることを、お祈りしています」
今、心が平穏から遠く離れてしまっている人がいたら、今度はわたしからこの言葉を届けたいと思います。